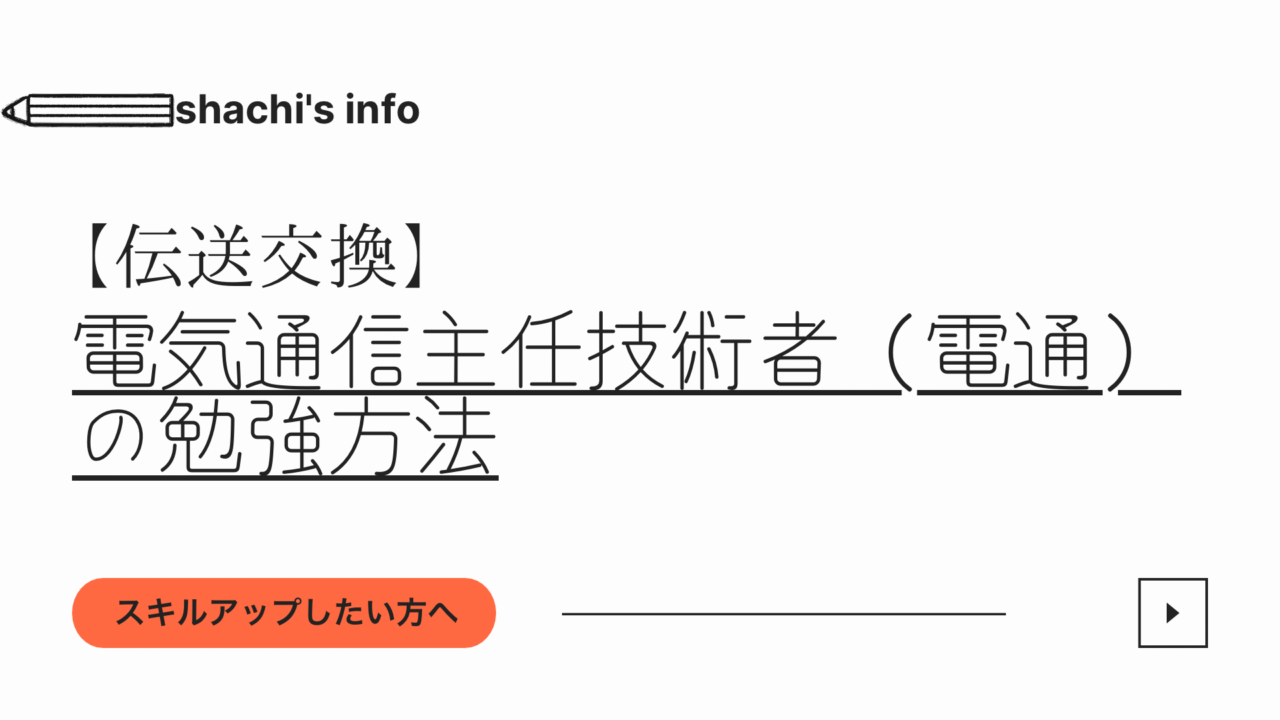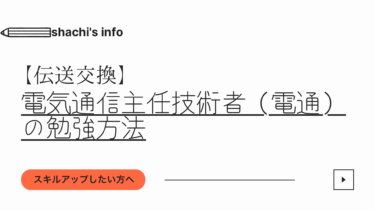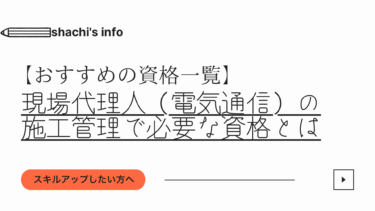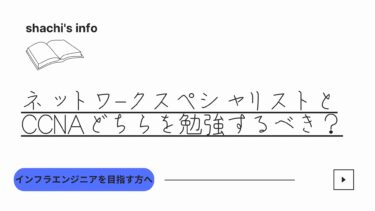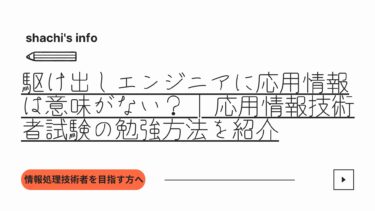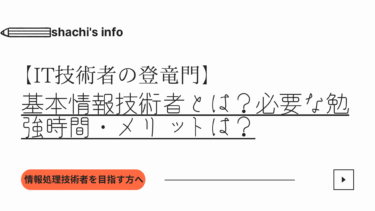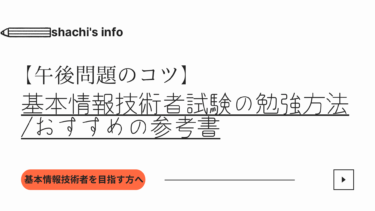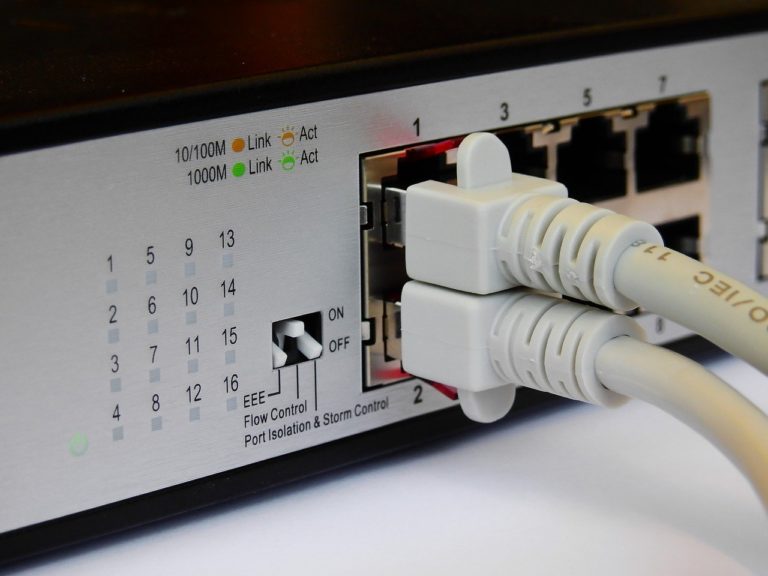・電気通信工事に関わる人。・施工管理でスキルアップしたい人。・どの資格を取れば良いか分からない人。 シャチ 10年間、電気通信の現場代理人として施工管理をしていました。 スキルアップしたいけど、「電気通信工事」の資格[…]

✔️電気通信主任技術者(伝送交換)の勉強方法
![]()
電気通信主任技術者(伝送交換)の勉強方法
全科目共通の勉強方法としては、
各科目毎に簡単な
✔︎勉強方法
✔︎出題傾向
を紹介していきます。
電気通信システム
・アプリを活用
基礎的な科目で簡易的な問題がメインになります。
基礎的な問題がメインなので、
「工事担任者」や「専門科目」の勉強の中で理解ができる問題もあるため、遅めの勉強で良いと思います。
- 電気通信用語
- 電子回路、三相回路
- インピーダンス系の「数式」や「計算」
- 文章に合う単語を選択肢から選択。
- 基礎的な計算問題・計算公式の選択。
伝送交換設備および設備管理
・出題頻度の多い問題や類似問題を統計
過去問を「10年分」解き、間違った箇所は定着するまで繰り返し解きました。
- 電話
- 無線通信
- 通信電力
- 施工管理
- 労働基準法
- 電気通信事業法
- ネットワーク系
- 情報セキュリティ系
※ その他にも、光ファイバの変調技術、PONシステム、デジタル変調、デジタル無線伝送、波長分割多重、TCP/IPプロトコル etc…が出題されます。
- 電気通信用語に関する正誤問題。
- 電気通信用語に関する穴埋め問題。
- 【☆頻出】信頼性の計算。

専門的能力(データ通信)
・出題頻度の多い問題や類似問題を統計
「伝送交換設備」同様に、過去問を「10年分」解き、間違った箇所は定着するまで繰り返し解きました。
- 暗号化
- ハードウェア
- ソフトウェア
- 伝送ネットワーク
- TCP/IP
※その他にも、電子メールシステム、ギガビットイーサネット、HTML/XML、IPv6、etc…が出題されます。
- 電気通信用語に関する正誤問題。
- 電気通信用語に関する穴埋め問題。

法規
・アプリや動物の参考書を活用
私は法規にあまり時間を割きたくなかったので、2週間前に過去問を繰り返し解き頭に叩き込みました。
前半で法規に取り掛かると、
他科目の学習により覚えたものを忘れてしまう可能性が高いため、試験直前の勉強と決めていました。
- 電気通信事業法
- 有線電気通信法
- 法律・規則などの文章の正誤問題。
- 法律・規則などの単語や数値の穴埋め問題。

受験科目毎の難易度
⬇︎ 電気通信システム
⬇︎ 伝送交換設備および設備管理
難 専門的能力
受験科目毎の難易度は、個人的に低い順から並べるとこのようになります。
受験科目毎の優先順位と勉強時間
⬇︎ 線路設備・設備管理[2ヶ月半]
⬇︎ 電気通信システム[1ヶ月(免除)]
遅 法規[2週間(免除)]
[※システムと法規は、「線路」を参考にしています。]
「専門的能力」と「伝送交換設備」は勉強範囲が多少被っている部分があるため、
優先順位を付けましたが、同時期に初めても良いと思います。

必要な参考書
過去問の繰り返しのみで合格することができましたので、参考書は特に必要ないです。
法規の参考書は、移動時や空き時間に利用できるのであっても良いと思います。
[法規]
電気通信主任技術者試験法規 これなら受かる 改訂3版/オーム社
:スマホで学習するときに画面が小さく、本の方が見やすいというだけなのでなくても特段問題ありません。
科目免除となる資格
一例ですが、取得している資格により下記の表のように科目免除となります。
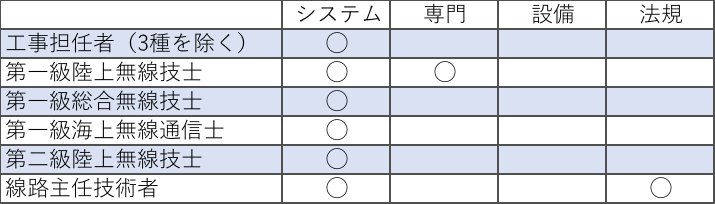

まとめ:電気通信主任技術者(伝送交換)の勉強方法
[優先順位]
- 専門的能力[3ヶ月]
- 線路設備・設備管理[2ヶ月半]
- 電気通信システム[1ヶ月]
- 法規[2週間]
不合格でも諦めず、何が足りなかったか次に生かすことが大切です!

合格できる勉強方法を知って、可能であれば一発合格を目指しましょう。
また、
「他の関連のある資格」や「線路・伝送交換」の両方の資格取得を目指している場合は、